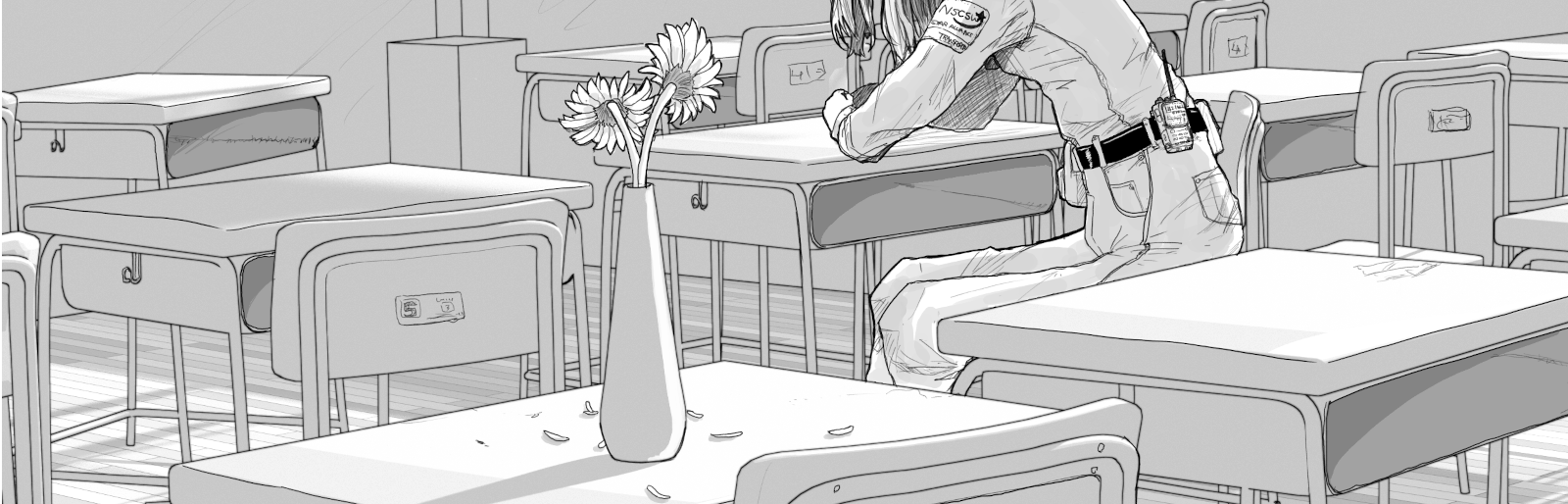補足
この短編小説はMisskey.artサーバーの内輪ネタとして書いたものです。
「知ってる?秒速2センチメートルなんだって」
「えっ、何?」
「artサーバーのLTLが流れる速度。秒速2センチメートル」
秋鹿はこういうことをよく知っている。豆知識を収集するのが趣味なんだ。加えてもう一つ。秒速2センチメートルという言葉は200年前の地球で流行ったアニメーションに由来するというのも当然のごとく知っている。
外の雨は止まない。予定では3時間後には停止することになっている。それまで俺と秋鹿はいつもの居酒屋で飲んでるというわけだ。
「おっちゃん、オランダモチョチョひとつ」
そう言うと手ぬぐいで鉢巻きしたおっちゃんが「あいよっ」と威勢のよい返事をしてモチョチョをすぐに焼いてくれる。オランダモチョチョはここのオリジナルで、中にマヨネーズとハムが入っているモチョチョだ。ベイクドモチョチョの定番フレーバーはアズキビーンズだけど、俺はオランダのジャンキーな味が好きだった。壁にかかった「オランダモチョチョ 100えん」の木札は秋鹿と出会った頃からそのままで、俺たちの他に注文しているお客を見たことがなかった。
「おまちっ」
焼き上がったモチョチョを載せた皿は長年の油が染み込んだ木のカウンターに無遠慮に置かれ、俺と秋鹿は手づかみでモチョチョを食べながらちびちびとホッピーを飲む。モチョチョ二つにホッピー一瓶、それで中身を三杯、これが俺の揺るがないいつものペースだ。
今日は雨だったからか、お客が俺たちだけだった。モチョチョとホッピーの瓶を裸電球のあたたかな光が包んでいて、それを見ると心の芯からあたたまるようだ。それらを飲み食いして俺の体は緩やかに座り心地の悪い椅子とカウンターに溶け込んでいく。
「見て。今日もMisskeyTimeが始まってる」
秋鹿が指差す先には公共通信端末があって、今日も色とりどりの絵文字がブラウン管に映し出されていた。それはまるで漆黒祭の灯籠のよう。
俺らが好んでこの居酒屋を選ぶもう一つの理由はこれだ。壁に据え付けられた真四角のブラウン管にはArtサーバーのローカル・タイムラインが映し出されていて、おっちゃんにお願いすれば1回50えんでノートを投稿することだってできた。でも俺らは学生で金がなかったから、投稿するときはアパートの共用回線をなるべく使うようにしていた。外ではこうして酒を飲みながらタイムラインを見て時間を潰すのが週に一度の楽しみだった。古文だとこういうのをROM専って言うらしい。
Artサーバーが復活したのはまさに偉業だった。ミスキー大学のサーバーにハックした二人の高校生が200年前に地球上に存在したMisskey.artサーバーの完全なホログラフィック・コピーを奪取してガニメデの入植基地全体につながる公共情報網上に当時の姿を完全に復帰させたのだった。
俺は地球上のY2Kカルチャー(2000年代から始まったアニメとコミックアートの黄金期だ)の大ファンだった。そんな俺がArtサーバーにのめり込むのにさほど時間はかからなかったし、いつも集合住宅のか細い通信回線に無理やりデータを押し込みながら、毎晩のように神絵師になろうとイラストを投稿してMisskeyTimeを過ごしている。
「今日はオンライン、300人だね」
秋鹿がホッピーを混ぜながらそうひとりごとのようにつぶやく。もう頬が赤くなっていた。
「オンラインが100人だったらカフェの会話。オンライン200人だったら普通の飲み会。オンライン300人だったら、立食パーティって感じだよ」
それが秋鹿の口癖だった。上手いことを言うもんだ。
じゃあ、1000人超えたら?俺がそう尋ねると。
「1000人超えたら、もう漆黒フェスだね」
秋鹿はそう言って笑って、また一口ホッピーを飲んでモチョチョをかじるのだった。
秋鹿も俺も、はじめはArtサーバーでリアクションを送り合ってるだけの関係だった。毎晩のようにイラストを投稿しては「絵上手人」とか「BIG LOVE」とかいった「あら〜」とかいうリアクションを送りあった。
一年前の漆黒フェスの日、チケットを無くして一人で狼狽している秋鹿を見つけた。俺は知り合いのふりをして上手いこと受付にいる要領の悪そうな兄ちゃんを騙して秋鹿を会場に入れた。秋鹿を連れてきたときはトップバッターのバンド、"THE BUCHU BOTTERES" のド鉄板ナンバー「神絵師の腕」のイントロのベースラインが大音量でかき鳴らされたところだった。俺と秋鹿は初対面で顔を見合わせ、二人でモッシュの中に突入していった。
フェスが終わってから飲み会の席で秋鹿がArtサーバーの住人で、実はお互い日々リアクションを送り合っていたとを知って驚いた。ずっとお互い初対面だったと思ってkたけど、随分と前から知り合いだったんだ。互いにハンドルネームを呼び合って大笑いした。なんて奇跡的な出会いだと思ったのだった。
そんな俺達だったから、付き合うまでも時間はかからなかった。
付き合ってからも俺達の関係はArtサーバーが中心だった。俺は秋鹿と出会う前から秋鹿の絵が好きだったし、秋鹿も俺の絵には必ずリアクションをくれた。秋鹿のイラストに描かれたキャラクターはどれも生き生きとした躍動感があって、生きている人間の表情をちゃんと切り取っている、そんな感じがあった。それが好きだった。わざとらしくない笑顔。魅力的なキャラクター。そこに存在するかのようにありありと光景を想像できる質感。そんな秋鹿の絵がたまらなく好きだった。
秋鹿も俺の絵をよく褒めてくれた。俺は俺の絵にそこまで自信はなかったけれども、俺が絵を投下するたび秋鹿は「性癖に刺さる」ってリアクションを返してくれて、それがなんだか笑えたんだ。
「早勢の絵の一番いいところは、上手く描こうと思ってないところだよ」
秋鹿はそう言ってくれていた。そうかな?俺は、上手くなりたいけどな。神絵師になるってのは、上手い絵師になるってことだろ。そのために練習を重ねなきゃ。そう言うと。
「練習を重ねていって、技術だけうまくなって、早勢のエモい感情が無くなっちゃったらさみしいよ。練習なんて止めて、好きな絵だけ描こうよ。早勢が伝えたいことは絵を通して私にちゃんと伝わってるから、もう練習なんて十分だよ。その伝えたいメッセージこそが、絵の魂なんだ。技術だけで魂のこもってない絵なんてつまらないよ」
そうやって八重歯を見せて笑う。その口元に俺は何度助けられたことか。
けれども、最近は複雑な気持ちを抱くようになってしまった。秋鹿がなんと言おうと、秋鹿の絵はとても上手い。それは誰が見ても一目瞭然で、秋鹿の絵は毎夜たくさんのリアクションやリプライを集めていた。それが彼氏としては嬉しく誇らしい気持ちもあった反面、古参のArtサーバーユーザーとしては秋鹿の絵ばかりが伸びていくのはあまり面白いものでもなかった。それが嫉妬だと認めるまで結構な時間がかかった。
もちろん、そんなことは秋鹿に限ったわけではない。今は第三次イラストブームと言われていて、誰も彼もが神絵師になろうと絵を練習している。Artサーバーでも何人も神絵師と呼ばれる人たちが集い、新たに生まれた。
俺も負けじと絵を投稿し続けたけど、秋鹿ほどにはリアクションが増えなかった。
大した数のリアクションがつかないのを見て、俺には才能が無いのだろうなって気づき始めていた。俺ももう子供じゃない。もうすぐ就職活動が始まる。いつまでも神絵師になりたいなんて事を言ってられなかった。昔はイラストを描き続けていくうちに俺は神絵師になれるって思ってた。現実はそうじゃない。人には向き不向きがあって、限界もある。一番近くで秋鹿を見ていて、それがよく分かったんだ。
飲みながらずっとそんな鬱々としたことを考えてしまう。おっちゃんは俺達が注文しないから、折りたたんだモチョ犬レース新聞を暇そうに眺めていた。目線を秋鹿に戻す。秋鹿はずっと公共端末に映し出されるMisskey Timeを目で追っている。
俺はおっちゃんに50えんを支払って、ノートを投稿してもらった。
"皆さん何でメシ食ってる人なんです?"
帰ってくるエアリプは、看護師だの、インフラエンジニアだの、犬のトリマーだの、イラストレーターだの、漫画家だの、様々だ。驚くような答えはない。みんな、当たり前に仕事をして当たり前に生活をしている。多分、俺もそうなる日が来るのだろうなと思った。そりゃ、俺だって選べるならイラストレーターや漫画家になりたかった。でも、そういう肩書が神絵師になるための必要十分条件かと言われると、それは俺にもわからなかった。神絵師ってなんなんだろう。
「〽食わず嫌いは 損をするって だから食え 神絵師の腕 何本でも生え変わる 神絵師の腕 だから食え 焼いて食え アメリカみたいなBBQ マヨネーズもかけてあげましょね」
秋鹿は乾きものをかじりながら「神絵師の腕」を口ずさんでいた。ご機嫌な証拠だ。
オランダモチョチョを五つも食べても雨は止まなかった。流石にジャンキーな味が好きといえども、マヨネーズ入りのモチョチョはそういくつも食えるものではなかった。雨に関しては規定の土壌水分量に達していないとかで、更に一時間の雨の延長が決まったと公共端末に通知があった。その間に秋鹿はだいぶ酔っ払ってしまったようで、耳まで真っ赤にしながらもタイムラインを見つめて嬉しそうにニヤニヤしている。カウンターには空になったホッピーが並び、おっちゃんの禿げた頭が電球を反射している。
「秋鹿は、大学を卒業したらどうするの」
「わかんない。でも絵で仕事が取れたら、それで生活したいと思ってるよ。今は絵を描くことしかしたくないんだ」
秋鹿らしい答えだったし、そうであってほしかった。秋鹿にはそうする実力と権利があるように思えた。そして、そんな人が自分の彼女であったとしても嫉妬心を完全に拭い去ることはできなかった。
それから数ヶ月。
俺はあちこちの町工場をまわって就職活動をした。今はガニメデでも第二次入植隊のための建設ラッシュで湧いていて、よほど難がある人間でも無ければ食っていくには困らない。それでもなるべく良い条件で働きたいから、なるたけたくさんの内定を受け取って選択肢を増やそうと苦心した。
俺は面接官の前でニコニコな笑顔を作り、「人間の活動領域を広げるために、ガニメデ上のコロニー建設に携わるのが子供の頃からの夢でした」と嘘っぱちな夢を語った。面接官はそれを聞いてやる気のある若者だと満足したように頷いた。私は絵が描くのが好きなんです、なんて話はどの面接でもしなかった。
その間も、秋鹿はついに一つも面接を受けなかった。本気で絵描き…つまり、神絵師、になろうと決めたらしい。
俺が内定承諾書に記された月俸を比べて、一番高いやつにサインをした頃のことだった。
友達と遅くまで就活完了会で飲み歩いて二日酔いだった。布団の中でどうにも身の置きどころが無く、頭痛に耐えながら右を向いたり左を向いたりということを永遠に繰り返しているその最中、秋鹿がノックもせずに勝手に部屋に帰ってきて、書類の束で俺の頬をぺちぺちと叩く。
一体なんだと吐きそうになるのを堪えて書類を手に取ると、そこには。
<<ガニメアンカルチャー交流隊 第一次クリエイター募集要綱>>
そう書かれている。
「次にやってくる地球人の入植者のためにガニメデの文化を発信するクリエイターを募集してるんだ。地球に行けるんだって!行き先は日本だよ!Artサーバー発祥の地だよ!」
秋鹿はそう言って目を輝かせているが、頭痛のせいであまり理解ができない。文化交流?Artサーバー発祥地?なんの話なんだ。
「地球なんて重力井戸の底に行ったら、ガニメデ生まれガニメデ育ちの俺たちなんか潰れちゃうよ」
そう反論するのが精一杯だった。今は何も考えたくない。ひたすら頭を締め付ける鈍い痛みに耐えている。
「でも、選ばれさえすれば地球でずっと絵を描いていられるんだよ?すごくない!?」
秋鹿は子供みたいに無邪気な笑顔で布団の上に馬乗りになってそう叫んでくる。実際、秋鹿は高校の時のジャージを未だに着てるし本当に子供みたいだ。俺は秋鹿の体重に潰されてモチョチョの中身が弾けそう。
「ね、二人で地球に行こうよ!Y2Kの爆心地で、私達二人で絵を描いて地球人たちにガニメデのことを教えてやるんだ!!絶対楽しいよ!!」
大きく開いた口から八重歯が見えていた。こういうときの秋鹿は遠慮がない。普段は漆黒フェスのチケットを無くして泣きそうになるようなメンタルの弱さなのに、絵に関してはどこまでも貪欲なのが秋鹿だった。それについていけなくて、つい本心を漏らしてしまった。
「地球ったって…。俺、内定承諾しちゃったし。それに、絵描いても全然数字伸びねぇんだもん。リアクションもリノートも。秋鹿とは違うよ」
一瞬、秋鹿の動きが止まる。
「数字を伸ばすために絵を描いてたの?」
秋鹿はそうやって、「おばあちゃんのお耳はなんでそんなに大きいの?」って感じの無垢な目で俺の顔を覗き込んでくる。やめてくれ。そういう目に俺は弱い。
「いや、違うけどさ…。でも、神絵師になるためには伸びる絵が描けなきゃ。俺は秋鹿みたいにはなれないよ」
「どうして?なんでそんな事を言うの?私は早勢の絵、好きだよ。大っ好きだよ」
秋鹿はそうやって布団ごと俺を抱きしめてくる。自分の絵が好きだとはっきりと言われて、二日酔いの頭でも理解できる感情の変化が俺の心の中にあった。一瞬、秋鹿と地球に行く姿を想像した……でも、だめだった。さり際に袖を掴まれるような、そんな最後のチャンスすら手のひらからこぼれ落としてしまったんだ。
「そんな事言ってもさ、実際俺の絵は伸びてねぇじゃん。俺の絵なんて秋鹿がもらうリアクションの一割もないよ。才能ないんだよ、俺」
「早勢が絵を描きたいって気持ちと、SNSで数字が伸びるってことと、関係ないじゃん。早勢の絵が好きな人がここにいるよ!早勢はその人のために絵を描いてくれないの?早勢は神絵師って言われたいから絵を描いてたの?」
「もー無理だよ。二日酔いでいきなりそんな議論ふっかけられても訳わかんねぇよ。一番訳分かんねぇのはその地球に行ってクリエイターになるとかいうその紙だよ。地球で絵を描くとか、本気で思ってんの!?」
「えっ」
秋鹿の攻撃が一瞬で止んで、それで俺はしまった、と思った。
「…そうだよ」
秋鹿は自信なさそうに言った。その秋鹿の顔は、あのとき漆黒フェスの受付で泣きそうになりながらバッグの中を手探りで探してるあのときの顔だった。
「だめかな?」
秋鹿はそう尋ねた。
だめじゃない。だめじゃないけど、その道は秋鹿にしか通れない道だよ。俺はそう言いたかったけど、もう声も出なかった。その理由は、ゲロを吐くのを堪えていただけではなかった。
秋鹿は無言で部屋から出ていった。
その日から秋鹿と合うことは少なくなった。それでも秋鹿は、会うたびに選考が進んでいることを笑顔で報告してくれた。でも、それでも。二度と一緒に行こうとは言ってくれなかった。それが何を意味するのかは知っている。その結末がどう迎えるのかも。
秋鹿は選考に合格した。季節はすでに冬に設定されていた。
秋鹿が選考に合格したのは当然だと思った。秋鹿はひたすらに絵を描き続けていた。俺は…。Artサーバーを見てはいるけど、絵を描くことはめっきり少なくなってしまっていた。それでも、たまに投稿すると真っ先に秋鹿からリアクションが飛んでくるのが悲しかった。
おめでとう!ありがと!いつもの居酒屋でそんな声が響く。秋鹿の友達やArtサーバーの知り合いが何人も秋鹿の祝賀会に駆けた。うちの団地から宇宙飛行士が出るなんて初めてのことだよ、なんて自治会長のおばちゃんまでがやってきて秋鹿にとびきり濃くしたホッピーを入れるのだった。
いつもは黙々とモチョチョをベイクしているおっちゃんも、今日は笑顔を見せてみんなといっしょにホッピーを飲んでいる。秋鹿ちゃんが飲みに来なくなると、寂しくなるねぇ、などと言っている。そんな事を思っていたのか。おっさんよ。
二次会、三次会と続いたところで、ついに秋鹿と二人になった。俺達が付き合っているのを知っている人たちは気を使って先に帰ってしまったのだった。その心遣いが、心に重くのしかかる。
二人で曖昧に家の方向に歩いた。右には川が流れていて、その音だけが深夜のコロニーに響き渡っていた。雪がうっすらと川向うの文具店の庇に降り積もっていて、いつだったかそこに秋鹿と行ったことを思い出していた。秋鹿はシースルーの万年筆を買って、俺はスケッチブックを買った。二人で河原に座ってお絵描きしりとりをしていたことを思い出していた。
「ごめん、一緒に行けなくて」
俺はそう言った。本心だった。
「いいよ。地球に行ったらガニメデにはもう帰ってこれないかもしれないし。そんな気楽に決めれないよね」
秋鹿はそう、当たり前の事を言った。しかし秋鹿がそんな事を言うのは当たり前ではなかった。秋鹿はいつだって絵に関しては子供みたいに無邪気で…。
「それに私は」
秋鹿はそこまで言って言葉に詰まる。続く言葉が別れの言葉になるだろうと、お互いに察した。
「…ごめん。私が好きだったのは、やっぱり君の絵だった」
それで、もう終わりだった。
それから秋鹿と会うことはなかった。俺は絵を描くことを完全に止めてしまった。
"軌道エレベーターから宇宙船に乗ったぜ〜〜〜。地球についたら、また連絡するよん!!!!"
そのメッセージを最後に、秋鹿はartサーバーから姿を消した。原子力イオンエンジンをふかしてガニメデ周回軌道からホーマン遷移軌道に移り始めた宇宙船は、黒い空を見上げてもどこにいるのかさっぱりわからなかったし、昨今は公共放送でもいちいちシャトルの発着を中継することはしなくなっていた。
秋鹿が再びArtサーバーに顔を出すのは早くても一年後。しかも、地球とは40分の遅延がある。光速度不変の法則がもたらす物理的限界だ。話題が次々移ろいゆくローカルタイムラインで40分の時差ではMisskey Timeに会話するのは難しいだろう。
俺は自室で大きなものが抜け落ちてしまったArtサーバーのローカルタイムラインをぼんやりと見つめる。
いつか秋鹿が言っていたことを思い出してメジャーと時計を取り出した。
目印になるノートを目で追い、画面を通り過ぎるまでの時間を測定した。だいたい、秒速6センチメートルだった。秋鹿はローカルタイムラインが流れる速度は秒速2センチメートルと言っていたけど、その数字よりも三倍も早い。
今この瞬間はアクティブユーザー数が300くらいだった。例えるならば、このMisskey Timeは華やかな立食のパーティ…秋鹿がそう例えていたのを思い出す。これが俺にとって違和感のない、通常のLTLの流速だった。
それに比べると、秋鹿が言っていた秒速2センチメートルのタイムラインは三分の一だから、単純計算ならアクティブユーザー数は100人以下…。例えるならば親しい友人とカフェで会話しているような、そんなタイムライン。
つまり。秋鹿が見ていたのは、カフェで静かに会話しているようなタイムライン。俺が見ていたのは、パーティみたいなタイムライン。俺は、秋鹿にとってふさわしいのは華やかなMisskey Timeだと決めつけていた。だけど秋鹿は静かに絵について語り合うほうを好んでいたんだろう。絵とリアクションの向こうにいる一人ひとりの生身の人間を大事にしていたんだ。秋鹿は、数字なんて見てなかったんだ。
だから、秋鹿はあんなに良い絵が書けたんだ。
神絵師の中で、俺の絵を見つけてくれたんだ。
俺はキラキラの絵文字が次から次へと流れていくタイムラインで華やかさに目が眩み、たくさんのリアクションをもらうことしか考えていなかった。俺にとってリアクションとはただの数字になっていた。その数字の向こう側に人間がいるなんて思いもしなかった。そんな当たり前のことすら忘れてしまった。
俺が地球に行かなかったからじゃない。ずっと前からもう、俺たちはすれ違っていたんだ。
それを秋鹿に伝えたいと思った。俺、ようやく分かったよ、って。そしたら、秋鹿はいつも笑顔で「なになに?」って子供みたいに無邪気に話を聞いてくれるはずだ。でも、もうそんなことはありえない。第一、星々の間で思いを伝えるのに光速は遅すぎるんだ。