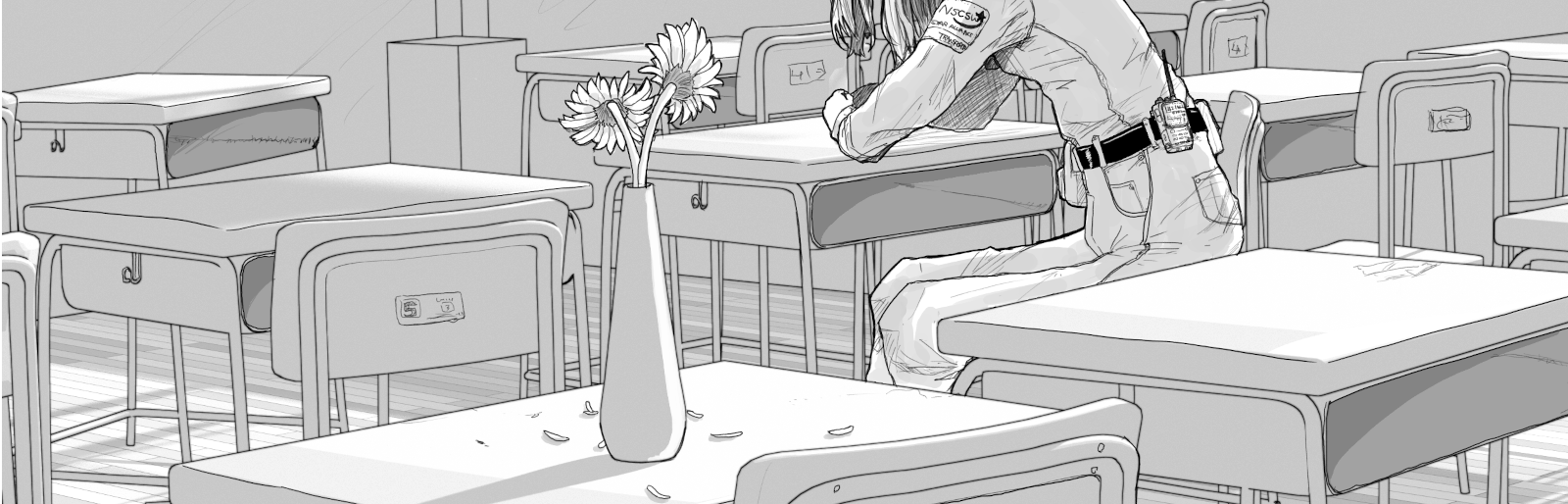高熱を出して寝込んでいるかのような、身の起きどころのない不快感だった。じゃっ、じゃっ、じゃっ、とチェーンがきしむ音だけが世界に存在しているかのよう。俺はひたすら苦痛に耐えている。もうチェーンの音しか聞こえない。もうハンドルに付いたギア・チェンジャーのノブしか見えない。
体を動かすたびに体の中から熱が湧き上がっている。それに追い打ちをかけるかのように高温多湿な気候が熱の発散を阻害している。加えて太陽からの輻射熱が皮膚を温めている。この街にその苦しみから逃れられる場所はそう多くない。だから日が落ち始めたのを見計らって出かけたのだが、まだ日が高いうちに出かけるのと苦痛は変わらないように思えた。
自転車を六キロも漕げたのは行く先につかの間の平和があると分かっていたからだ。エアコンという文明の利器によって保たれた快適な空間。しかも、部外者が自由に出入りすることを社会的に許されている。ここが重要だ。
坂道で自転車が転がらないようにそっとスタンドを立て、すぐに本屋に入った。入った瞬間に人類の偉大さを感じる。体の隅々まで冷気が行き渡るようだ。
俺が本屋に行くことになったのは、主に矢島のせいであった。俺は矢島に本を貸した。しかしそれは戻ってこなかった。単純な話であった。もう一度読みたくなって返してくれ、と言ったが、一向に返す返すと言いながら何週間も経った。矢島のことだから、大方無くしたか汚したか。最終的に「文庫本一つに何度も催促してがめつい」とまで言われて俺は俺が矢島に本を貸してしまったのが間違っていたのだろうな。
"ハローサマー、グッドバイ"
本が置いてある位置は案外すぐに判明した。なぜならばこの本屋で買ったのだから。私が前回購入したその場所そのままの位置に、見慣れた本があった。しかしその所有権は私には無く、私は再び対価を支払わねばならぬというわけだ。
しかし目的のものだけ買ってすぐに本屋を出るわけにはいかなかった。しばらく立ち読みして体の芯まで冷やしてやろうと思ったのだ。俺が六キロも自転車を漕いできたのは、そういうことだから。そう、六キロも。財力のない高校生に支払えるのはその行動力だけだったというわけ。
だから、俺は用もないのに見たことも聞いたこともない作者の文庫本などを手にとって買うふりをしたり、雑誌コーナーに行って買うあてもない中古車や中古バイクの値段を調べるなどしていた。その時も片手に「ハローサマー、グッドバイ」を持ったままだったのは、立ち読みして出ていくんじゃなくてちゃんと買いますよ、と店員にアピールする目的があったとも言える。
「早勢じゃん」
左上の方で馴れ馴れしい声がしたと思うと秋鹿がいる。
「何してんの?」
秋鹿は本屋の中でアイスを食いながら喋っている。常識のない女だ。
「バイクの免許、取ったの?」
そうやって俺が持っているGooBike東北版九月号を中指で指す。人差し指と親指でアイスの棒をはさみ中指で俺とGooBikeを交互に指し示し、もう一方の手に幼稚な手提げかばんを持っている。
「本当は進路が決まった人しか、車校には行っちゃダメなんだあ」
秋鹿は俺が返事をする間すら与えず次々と言葉をねじ込んでくる。
「良いんだよ。秋鹿が言わなきゃバレないんだから」

このあたりで通える自動車学校は一つしか無かった。免許を取ろうと通えば嫌でも同級生と鉢合わせする。だからバレるのが嫌でわざわざ夏休み前に学校が終わった後にちまちまと一時間ずつ通っていたのだが、同じことを考えていたのが秋鹿だった。秋鹿は車の免許を取りに行っていたが、秋鹿だって進路が決まっているわけではなかった。だから共犯だ。バレたら困るのはお互い様なので脅しになるわけがない。
「バイク、買ったの?」
「買ってない。これから買おうとしてるからこれ読んでるんだよ」
「ふうん」
秋鹿が手に持っているのはアイスじゃなくて、ただの棒、になっていた。食うのが早い。
「じゃ、今日バイクじゃないんだ」
「当たり前だろ。高校生でバイクなんか買えるかよ。買ったとして地元で乗りまわせるかよ」
「じゃあ買ったら乗せてね」
「そーゆーと思ったわ」
そう言うと秋鹿は、あは、あははははは、と大笑いした。恥ずかしくなるような笑い声だった。何がおかしいのか。箸が転んだからか。
なんだか恥ずかしくなってそして嫌になって、俺は苦痛の旅程を経た末にたどり着いたこの快適空間を即座に後にすることになってしまった。会計を済ませてバッグに本を突っ込んで外に出ても秋鹿は話しかけてくる。
「ほんとはバイクより車のほうが好きだけど。バイク、雨降ったら濡れるしスカート履けないでしょ。夏は暑いし」
こういう距離感のバグった女は嫌いなんだよな。もういっこ嫌なのは、まあ、ふつう夏休みに同級生女子と偶然出会ってお話をするという経験は嬉しいものなのだろうけれども、秋鹿にはすでに彼氏がいたからだ。すでに他人の持ち物になっている女と話しているほど惨めでつまらないことはない。
「夏が暑いのは当たり前だろ」
っていうか、お前を乗せるためにこの世にバイクが存在してるわけでもねぇーし、とも思った。でもそれは付け加えないでおいた。だから俺はどうやってこの会話を終わらせて帰るかということに脳の計算資源を費やしていた。
「花火大会、いかないの?」
いかない。花火大会がある、というのは考えないようにしていた。考えないようにしても考えてしまうと言ったほうが正しいか。今日、自転車でここまで来た理由は本だけじゃなかったのは認めるし、もしかしたら誰か女の子と会うかもな、と期待しなかったというわけでもない。でもそれは秋鹿とではなかった。秋鹿と、つまり彼氏彼女の居る誰かと話すくらいだったら、劣情の海に揺られながら自転車を漕いでまた六キロ帰ったほうがマシだと思っていたのだった。だってそうだろう?花火大会っていうのはそういうもんだ。
「俺は行かないけど」
「ふうん。行かないんだ。それも、いいかもね」
秋鹿はただ、そう言ったのだった。
「お前、彼氏いるだろ。彼氏と行くだろ」
「知ってるの」
「高校に迎えに来る車、どう考えてもお前んちの親が乗る車じゃないしな」
それも俺の卑屈な心に刻まれた影の一つだった。型落ちの高級車の車高を下げて爆音で音楽を流して迎えにくる彼氏。それを見て、馬鹿みたいだ、俺はそんな大人になるまいと考えているが、しかしそんな馬鹿でも車は持ってる。秋鹿という彼女もいる。でも俺には何もない。それも俺の卑屈な心をさらに腐らせている。
「あたし、花火大会、行かないよ」
「なんで?」
「だって…なーんにも面白くないんだもの」
と、それを聞いて意外に思うと同時に合点もいった。秋鹿の話とは、要約するとそういうことであったのだった。何か理由があって彼氏とは行けないのだろう。喧嘩したのか何なのか。
「ね、行こうよ。自転車、ニッケして」
「はぁ?どこに?」
「どこでも良いよ。あ、じゃ、あそこ行こ。西野山公園。花火見えるらしいよ」
「花火、見たいんか?」
「そ。今はね。早勢とね」
最後の言葉には反応しないこととした。惨めすぎるから。
秋鹿は幼稚なバッグを勝手に自転車のカゴに入れ、二人乗り用のステップ(もちろん違法なやつだ、なぜこんな物が売られているのかわからない)に足をかけた。秋鹿が肩に手を乗せる。汗ばんで暑かった。もしくは、俺の肩が湿っているのか。
じゃっ、じゃっ、じゃっ。また自転車を漕ぎ始めた。秋鹿が重かった。
「どうすんの?高校卒業したら」
「俺?わかんねぇ。お前は?」
「わかんない。短大行くかも」
「なんの?」
「看護とか。わかんないけど」
「わかんないのに進学するのか?金もったいないとは思わないのな」
「だって…いいじゃない、そんなの」
いいじゃない、って、お前。その学費払うのはお前の親じゃねぇの?と言いかけて言葉を飲み込んだ。口うるさい自分の母親の顔がとっさに浮かんできたから。そうだな、そうかもしれない。別に、どうでも良いかもしれない。俺だって仕事をするために生きていこうとしているわけではない。今のところはバイクを買うために生きてるのだから。
「そうだな。どうでも良いかもな」
何か返事があるわけでもない。肩に置いた手もそのままで変化が無かった。
「良い時間になったね」
『良い』の意味はわからなかったけれど、そうだ、良い時間なのだな、と思った。空は夕焼けだった。オレンジの雲がまだらに浮いていて、その背景は深い紫、そして宇宙を感じさせる青から暗闇へと続く色彩の階調が天の向こうまで伸びている。
高校の前の住宅街を通り抜ける。誰かの家でカレーを作っている。鍋に蓋をする金属のこすれる音がかすかに聞こえる。ハンドルを握ってそれら一つ一つを踏み潰していく。図書館の脇を走り、墓場の横を通ったら田んぼの横の舗装された道に出る。ここまでくればもう誰と会うこともない。夕日に稲穂が頭を垂れて礼をしている。人生であと何度こんな事を繰り返すのだろう。
「バイク、買ったら乗せてくれる?」
秋鹿はまた同じことを言った。でも、今度は聞き方が違っていた。縋るような声だった。
「そのときにはもう、お前は関東とか看護学校とか行ってんだろ」
「そっかあ、そうかも」
河原に出るとすぐに橋が見えてきて、その奥にコンクリートの製造工場がある。今日はミキサー車が一つも止まっていない。
「早勢はどうすんの?就職するの」
「俺?さあ、どうしようかな」
今は八月だけど、そのうちに一〇月になって、十一月になって、そして枯れ葉に包まれてから冬が来る。八月の夕焼けが落ちていくように、季節も雪の底に落ちていく。良い時間はあっという間にすぎる。長い冬が終わってようやく光が差し込んで雪が溶けたら、この街ともおさらばだ。少しだけ残る雪解けの匂いをにわかに感じつつ、バイクの免許だけ持ってどこかに行くことになる。進路、決まってねぇけど。
「俺もこの街には居ないだろうと思うけど」
そう言うのが精一杯だった。もしかしたら、秋鹿と一緒にバイクに乗るような未来もあったかもしれないと思った。けれども、実際にそうはならない。だから何だ?そこに何か意味があるわけじゃない。単に、お互いに別々に生きていたというだけだ。
秋鹿とは中学も一緒だった。秋鹿はバレー部だった。俺は卓球部だった。一緒の体育館であの夏も部活をしていた。大きく開けた出入り口から見た外の景色が、あまりにも眩しかった。秋鹿はそんなところで、ばしん、ばしんとバレーボールをつまらなそうに床に叩きつけていた。俺はセンパイに言われてネットを何度も直していた。ただ、それだけだった。今一緒に居るから何か意味のない予感がするだけであって、実際は中学のときから何も変わっちゃいない。
西野山公園に続く坂道では流石に降りて歩いてもらった。自転車を押して公園にたどり着くと、錆びたブランコと滑り台、そして雑草がまだらに茂った砂場があった。誰かが来るのを待ちわびているように思えた。
そのブランコに座ってケータイで時間を見る。始まりを知らせる小さい花火が最初に一つ、そろそろ上がるはずだった。
あと半年かそこらで大人に片足を入れてしまうと思うと息が詰まった。俺は何も経験していない。俺は、俺の十代は…。なんも無かった。十代が終わるまであとたったの二年。バイクがほしいと教習所に通いながら中古車情報誌を見る。そうやって生きている。それ以外に何か大切なものを手に入れるとしたら、この街の外に出ないといけないだろう。なんとなくそんな気がした。だって、この街には何もなかった。本屋も一件しかないし、CDが買える店も無かった。カラオケに行くには電車で三十分。映画を見るには電車で一時間。この街は空虚だった。
ただそこには誤謬があり、それはそうあってほしいという俺の願望から生まれたことを知っている。空虚な街なのは、俺にとっては、だ。秋鹿に関しては、何かを持っている。顔も知らない秋鹿の彼氏にも。俺には…。やっぱり何も無かった。そして次の街でも、結局、この街には何もなかったと思ってしまうのかもしれない。いつまでも人と比べて腐っていくのだろう。それが俺の人生なのだろうか。
思い出したようにバッグに手を突っ込んで紙の箱を探り当て、そこからタバコを一つ取り出して吸った。それが秋鹿とこの街に対する、背伸びしたささやかな抵抗のつもりだった。隣のブランコに座る秋鹿はそれを、ちらと見ただけだった。それで俺の抵抗は終わりだった。
「あたし、この公園で小さい頃よく遊んでたよ」
秋鹿が乗って久しぶりに動き始めたブランコが苦しそうな音を立てると、なんだかブランコが可哀想に思えた。子供が少なくなり、誰も来なくなった公園。ブランコにとっては錆びついた体であっても乗ってもらうほうが嬉しいのかもしれないが。しかし、ぎいぃ、ぎいぃ、という幽霊が生前愛用していたミシンを丑三つ時に踏んでいます、みたいな音はさほど心地よくもなかった。タバコも残り少なになったなと思って寂しくなったときだった。
ばん、と花火の音がした。それからやや間があって、ばん、ばん。と連続して音がした。光も煙も見えなかった。
「もう少しで始まるかな」
秋鹿はそう言い終わらないうちに小さく、おっ、と声を出し、続いてビシッ、ばしっ、という音がして、それからどすっ、と鈍い音。
振り向きざまに見えたのはジャラジャラとチェーンが秋鹿の顔めがけて一直線に落ちてくる光景で、地面には秋鹿はブランコのチェーンともみくちゃになって転がっていた。朽ち果てたブランコの根本にある可動部分はもう秋鹿の体重を支えることはできなくなっていたのだろう。
秋鹿は顔を手のひらで覆って踞っている。いつもだったら恥ずかしさを紛らわそうと笑い出す秋鹿が何も言わないのが事の重大さを物語っていた。
「大丈夫か?」
とっさに言葉が出たがそれは本当に秋鹿を慮ったものではなくて脊髄反射的なものだった。白くて柔らかな腿に赤茶けた色が優しく乗って…。ケーキにゆるくて赤いクリームを絞ったかのように垂れていた。
秋鹿が顔を覆う手をゆっくりと退けると、血がべっとりと付いている。チェーンが頬を引っ掻いたようで、傷口は鋭利だった。なにか傷口を押さえるものは?とっさに考えて、汗を拭くために持っていたタオルで頬を覆って圧迫した。あまり清潔ではないかもしれないけど、ないよりはマシだろう。
「とりあえず血が止まるまで抑えているから」
そう言うと、秋鹿は目線で分かった、と合図して小さく頷く。強く抑えた顔が歪んでいる。タオル越しに頬の柔らかさを感じる。
「バッグ、とって」
秋鹿がそう言って自分のバッグを顎で指す。タオルを抑える手をそっと離して秋鹿に引き継ぎ、秋鹿の幼稚バッグを持っていった。秋鹿はそれを開けようとするが片手では無理だ。手伝ってマイメロ(か何か)のキーホルダーが付いたファスナーを開けてやる。すると、どういうことだろう?中から出てきたのは大きなガーゼと絆創膏のセットであった。なぜ?こうなることを予見していたのだろうか。それとも、看護の短大に行くことが何か関係している?
「いつもこれ持ってんのか?」
そう聞くと、うん、うん、と曖昧に秋鹿は頷いたあとで、いや、そうかな?と言いたげに首を傾げた。秋鹿自身、よく分かってはいないらしい。
「早勢のバッグには、タオルと本が入ってんだね」
秋鹿はタオルを抑えたまま、喋りにくそうにしていて。
結構な量の出血があったと思ったが、意外にも血はすんなりと止まった。恐る恐るタオルを取るとまだ傷口からはすこし血が滲んでいる。頬は血で汚れている。ガーゼを傷口にあてて絆創膏を貼ろうとしたがハサミがない。仕方なく一番大きな絆創膏を貼ったらちょっとばかり大げさで、いかにも大怪我をしたような感じになってしまった。
俺が直接手を下したのではないにせよ、そこに居る男は俺だったのだから、何か罪悪感を感じるべきだったのかもしれなかった。けれども、俺が思っていたことは真逆だった。
絆創膏を貼った秋鹿を見て美しいと思った。乱暴に扱ったらすぐ壊れてしまいそうな、弱くて華奢な秋鹿が美しかった。
きっと、学校の前であの粗雑な車に乗り込む秋鹿とは別の中身が入っているのだろう。
「ありがとう」
秋鹿の茶色の目が俺の目を射た。
茶色の目が宝石と一緒に浮かんでいる。闇と深淵のはざまに。唐突にその宝石の世界に住んでみたいと思った。朝に海辺で水を汲み、庭までバケツで持ってくる暮らし。そして夏が訪れ、過ぎ去り、枯れ葉が吹き上がってから凍える冬がくる。
「早勢」
きっと君は東京に行ってしまうだろう、誰かがそんな歌を頭の中で歌っていた。秋鹿は手を伸ばせば届くけれども、実際には永遠に届かない距離だった。でも、今この瞬間はどうだろう?手を伸ばさずにはいられなかった。だから手を伸ばす。指先で宝石の白い丘に触れる。そして絆創膏を手で包む。それに対する秋鹿の言葉。
「何、してんの?」