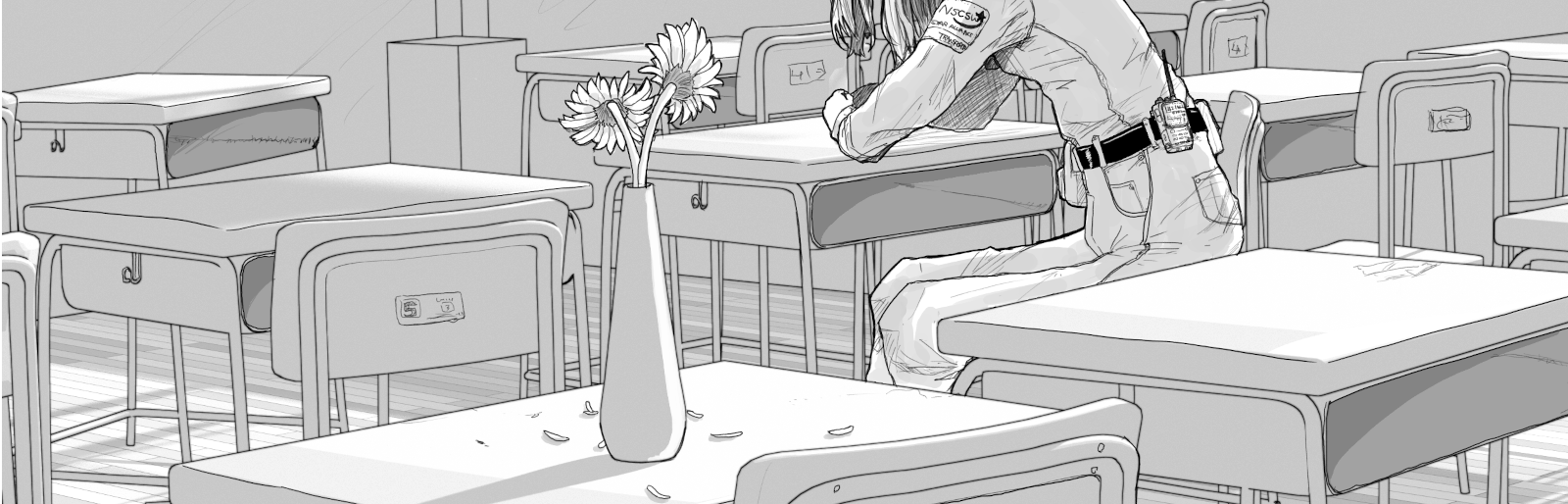クーラーが効いている快適な車内を降りて改札を抜けるとやはり真夏。日差しがじりじりと両腕を照り付け、すぐに髪も首周りも熱く焼かれたようになった。長い階段を下りてようやく駅前に出ると、そこにはひときわ大きなカエデの木がロータリーの真ん中から飛び出しており、今もなおアスファルトを破きながら根を伸ばしている。木を切るのも抜くのも、難工事になりそうだ。
そのカエデの向こう側には石畳と、さらにその奥に鳥居と薄暗くて長い階段がある。薄暗くなっているのは鬱蒼とした林が太陽を遮っているからで、そこが立っているだけで汗が溢れ出る世界から逃れる唯一の避難場所であった。
電車を降りてからも、右や左をきょろきょろと見回しつづけ落ち着かない知り合いの女(Aliceとする)を「おいで」と手招きして陽の下に導いた。まるで子供を相手にしているかのようだ。
Aliceは何歩か私から離れた位置をちょこちょこと付いてくる。「三尺下がって師の影を踏まず」ということではなく、単なる挙動不審である。
そもそも、私がこのクソ暑い世界に降り立った理由はAliceの用事の付き添いであるが、Aliceの顔には特に申し訳無さもない。付いて行けと言われたからそうしています、という体だ。実際、それはAliceの目から見れば そのとおりだった。
Aliceの姉(Bettyとする)から連絡があったのは突然のことだった。知らんメールアドレスから件名:「Aliceの姉です」とメッセージがあり、私は驚いた。Aliceに姉が居ることは最近になって知らされていたがまさか人間の言葉を話して現代人のように電子メールを扱える程度の常識人であるとは思わなかったからだ。しかも、です、ます口調を扱えることから基本的な会話のスキルもあるということだ。
一方でメールの内容はややぶっきらぼうで、要約すると「Aliceに大事な用がある。しかしAliceは電車に乗れない。しかるに、大変手間をかけて申し訳ないが、Aliceを家まで連れてきてほしい」とのことであった。会ったこともないのにずいぶんと図々しいなと思った。私はAliceの保護者ではない。ただ、高校生だったときから実質的にそう扱われていた。
「Aliceが電車に乗れない」というのも特に驚くことでもない。Aliceは病的なまでの方向音痴であったからだ。高校三年生、十七歳になっても、自宅から高校に至るまでの道に迷い授業に遅れることがままあった。その時も高校の教師から私のケータイに電話がかかってくることがよくあった。その時から実質的に私が保護者であったのだ。Aliceのたった一人の家族であったBettyも、その時私は存在すら知らなかった。その時にBettyの存在を知っていたら、私も全ての面倒をBettyに押し付けることが出来ただろう。私は呼び出される度に上司に嫌な顔をされて会社を抜け出たのだ。
そしてBettyもまた、私がAliceの保護者だと思っているのだろうなという感覚は文面から伺えた。
Aliceは高校を卒業してから定職に就くわけでもなく、何らかの教育を受けるわけでもなく、かと言って何かやりたいことや目的がある風でもなかった。身よりもなく定職もなくどうやって暮らしているのかは謎だ。ただ毎日ぶらぶらとしているだらしない女だという認識でいる。そして今も私の後ろをコバエのようにひょこひょこと揺れながら付いてきている。
道路から放射された熱線が体を貫く駅前の通りを過ぎ、古めかしいアーケードを通り過ぎたあたりにBettyの家はあった。木造で瓦の屋根の家や商店が並ぶ一帯の端にある。それぞれの建物は年季が入っているがきちんとした手入れがされてあった。行政が古の街並みを残そうと金を使っているのだろうことがうかがえた。この辺りの家々の敷地は歪に細長く、おそらくは長屋だったのだろう。
玄関は北側、日陰に位置していてここでようやく一息をつき、私は呼び鈴を押した。
ピンポーンという聞き慣れた音が聞こえると思ったが、実際にはべりりりりりりり、と汚い音がした。豚が落とし穴に落ちて抗議しているみたいな音だった。
しかし反応が無かった。Aliceは私を一瞥したのち、おもむろに玄関をガラガラと開け、無遠慮に家の中に入っていった。Aliceにしては強引だなと思ったが、しかし家族の家だから元々遠慮は要らないということなのかも知れない。ここまでたどり着けないだけで、ここに来たこと自体は何度か経験しているのかも。
玄関を開けた瞬間、一気に冷気が流れ出てきた。冷蔵庫の扉を開けたかのような。
家の中は暗く、冷房の低いうなり声だけがかすかに聞こえる。あらゆる窓には黒いビニールのようなもので目張りされており、唯一の明かりは小さな裸電球であった。
なんだかカビのような匂いがするし埃っぽい。奥に進むのを躊躇していると、ずかずかとAliceが進んでいく。Aliceは普段はおどおどしているが、勝手を知ったところだとこうも大胆になるらしい。
Aliceを追うが、いたるところに分厚い本や布、こけし、熊の木彫り、エッフェル塔を模した置物、2x4材などの雑多なものがほこりをかぶって山積みにされている。行く道は困難を極めた。額を棒で思い切り叩かれてなんじゃこいつはとよく見るとスキー板であった。エッジで額を切る所だった。危険極まりない。こんなとこに住んでるとは、さすがAliceの姉なだけある。
きしむ階段を上った廊下の一番奥に壁が大きく窪んだ一角があり、最初は荷物がまた積まれているなと思ったがAliceがその前で止まったのでようやく気づいた。荷物だと思ったそれは顔を上げて私を見つけると、読みかけの本を手に持ったまま微笑んだ。
「どうもすみません、お手数をおかけしてしまって」
と尋常の調子でしゃべり始めるのBettyを見て私は拍子抜けした。
ただしよくよく見ると奇妙な光景であった。ランプを吊り下げ、机の上に山ほど本を広げており、ぶ厚いコートを着込み、頭には絵本の中で魔法使いが被るような妙な帽子を被っている。その顔はやや欧米人の血が混じっているように思え、美形だった。一方Aliceは典型的な日本人顔で、本当に姉妹なのだろうかと勘ぐってしまう。
狭い通路で椅子もない。私とAliceは立ったままでBettyの話を聞いた。
はたして、Bettyの重要な用事とは「幽霊探知機」なるものを渡すことであった。Bettyが手渡したその機械の外観は古めかしいめっきが施された、何十年か前のカセットテープのポータブルプレイヤーのようなもので、緑色のディスプレイにいくつかのボタンやスイッチが付いたような、掌に何とか収まるくらいの大きさの代物だった。
「道中、きっとこれが必要になることがあるから、大事に持っていてね」、Bettyはそう言った。Aliceは分かっているのか分かっていないのか、ぼやんとした顔をしたままうなづいたのち、幽霊探知機を手にとってくるくる回しながら観察しているあいだ中、唇をとがらせていた。
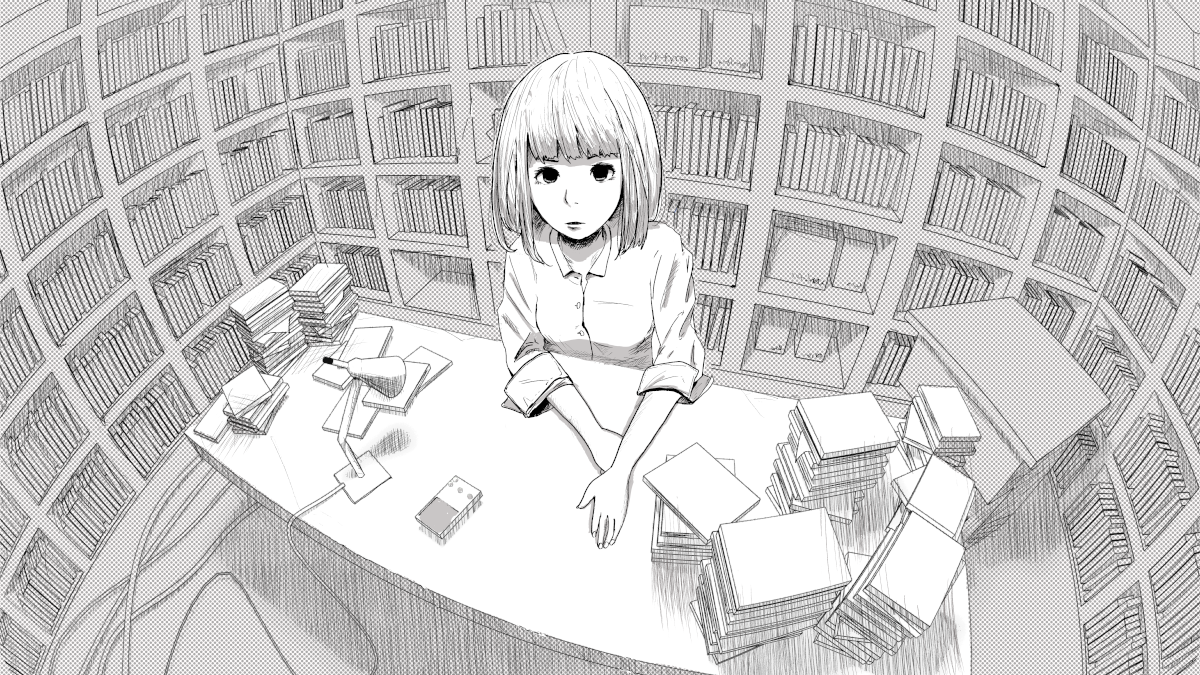
ここからが面倒であった。
数日後、私はAliceとともに東北へと向かう新幹線に乗っていた。駅でビールなどの酒をいくつか買ってリュックにつっこみ、ちまちまと飲んだ。Aliceはつまらなそうに窓の外を見ている。
酒も切符代もBettyからもらった金で買ったものだった。一応、多少決まりが悪いという思いもあって
「飲むか」
とAliceにも酒を勧めた。Aliceは黙って頷き、缶を手に取りちびちびと飲み始めた。その飲み方も特にうまそうなわけではない、単に液体を摂取していますという面で飲んでいる。一緒に酒を飲んでも面白くない、という点では今まで会った女の中でずば抜けていた。
しばらくして窓から先の光景は田んぼのみになった。すでに飽きつつあった。多少多めに買った酒の残量だけが私を支えてくれている。
AliceとBettyの二人に親族はおらず、二人だけだった。それは知っていたが、改めてBettyから聞かされた。
Bettyは高校を卒業してすぐ、地元を離れて働き始めた。実家に一人残ったAliceはBettyからの仕送りを受けて暮らしているらしい。つまり、これで謎が一つ解けた。AliceはBettyによって養われながら、定職にも付かず、ぶらぶらとしているというわけであった。働かざるもの食うべからず。特段の事情があるわけでもなく働かざるして世間で生活させてもらっている、その恩義を分かっているのか分かっていないのか、Aliceは今もぼやんとしている。
試しに、幽霊探知機を改めて眺めてみた。スイッチの一つ一つを見ると、Sensitivity, Amplifire, Direction, EMP Charge, などと言った単語が振られているがそれが何の機能を有するのかさっぱりわからない。Bettyからもその点は特に説明は無く、大事に持っていろと言われたのみだった。もっとも、言われたのはAliceであるが、Aliceがものを大事に保管しておくということ自体が不可能であるから私が持っているしかなかった。
Aliceの母(Cherylとする)と父(Davidとする)が姿を消したのはBettyが高校を卒業する直前であった。行方はBettyも把握していないとのことだった。
酒を飲んだせいもあるかもしれないが、列車の中は暑くて汗が滲んでくる。弱冷房というやつだろうか。冷房が強すぎると騒ぐ女子供に配慮して十分な基礎代謝のある成人男性が暑いのを我慢する。この世はそういうことの連続だ。それから逃れるには酒しか無い。酒を飲んでいっとき、面倒を忘れることしかできない。
暑いのを我慢しているうちにすぐに眠くなった。今日の朝は早かったのだから。夢の中で俺は砂漠の惑星を歩き、宇宙人と握手していた。
CherylとDavidは東京で家庭を持ったが元々は別の土地で二人、小さな事業を営んでいたらしい。それが何であるかは昔のことなのでBettyにもわからないとのことであった。
BettyはCherylとDavidの失踪後、二人の足跡を追って手がかりを集めていた。やっとのことで見つけたのがその会社の所在地だった。その場所が今も残っているのであれば、CherylとDavidが現在どうしているかを知る手がかりがあるかもしれない。だから、行ってきて。
Bettyはあの日、Aliceを通じて、私に、そう伝えたのだった。
「Aliceはご存知の通り方向音痴ですよ。お姉さんが行ったほうが良いのでは」
私はそう反論したのだ。当然だ。
「それはもちろん承知しているのですが、それでもAliceに行っていただきたいのです」
飲み込んだ言葉を腹の底からひねり出すような言い方だった。ぶるるっ、と体が震えた。
その時BettyはAliceにではなく私に話していた。
嫌であった。心底嫌であった。
それでも、最終的に請け負ったのは
「これであなたにお願いをするのは最後になります。ですから、最後のお願いということになります」
そうBettyが言ったからだった。
これが最後であとはBettyが面倒を見るということなのだろう。なにを偉そうにこれが最後のお願いということになります、などと言っとるんじゃ、最初からそうしろ、と思う。実際そう言いかけたが、「旅費としてお使い下さい」と渡された厚みの感じる封筒を受け取ってそれをすぐに飲み込んだ。
新幹線を降り、Aliceの手を引き、電車を何度か乗り換え、ようやく目的地に降り立ったのは昼頃だった。
東北はまだそこまで夏という感じではなかった。ただ、温泉街であったために硫黄の匂いがあたりに立ち込めていたのが多少不快ではあったが。その土地は観光産業(温泉街)が主力であって、その他は伝統工芸品(こけし)が売られている。それ以外の産業は無い。山間に古い旅館が立ち並ぶばかり。ここで一体なんの事業をしていたのだろうか。
Bettyからもらったメモ書きの住所の所に向かうと、そこは単なる土産物屋であった。
中に入ると「いらっしゃいませ」という発音とは裏腹に、動くのが面倒くさい、ああ面倒くさい、さっさと買って出てってくれと言いたげな目の細いおばはんが出てきてこちらを咎めるようにじっと見つめていた。
「あの、お聞きしたいことがあるのですが」
「はいなんでしょうか」
「このお店はいつからやっていますか」
「朝は一応九時から開けてますけど」
「いや、そうじゃなくてね、創業何年とか」
「はあ?」
ここでおばはんは、なにを言っておるんですか?あなたは?客ではないのですか?客ではないのにこの私を店に立たせたわけですか?みたいに細い目を剥いて咎めるような表情に一転チェンジした。
「以前、シー・アール・デー企画という会社がここに入っていたようなのですが、知りませんか」
「シー…なに?」
「シー・アール・デー企画」
「いっやぁぁあ、しーりませんよぉ、そんな英語の会社なんてね、ここらにはありませんよ。うちはね、あのね、うちは三代やってるんですよ。ここで。三代土産物屋ですよ。そんな会社なんか、いや、しーらないですよぉ。聞いたこともない」
Bettyが集めた情報とやらは間違っていたのだろうか。
「他には?」そう追い打ちをかけるおばはんから逃げるように外に出て途方に暮れた。半日かけてやってきたのに、およそ一分でその目的が打ち砕かれたように思えた。
いや、もしかしたら住所が多少間違っているだけかもしれないな。でも足で探せってのかな?Bettyはこの旅には不釣り合いなほどの厚さの「旅費」を持たせたが、それはつまり、この厚み分働けということなのだろうか。
一帯はむやみに広く、おばはんの店以外にも土産物屋や蕎麦屋、温泉宿がごちゃごちゃとひしめきあっている。その一軒一軒に対して私は聞いて回った。質問は端的に、
「シー・アール・デー企画という会社を知りませんか」
と伝えた。住所(おそらく誤っている)以外にはそれしか情報が無かった。
道の反対側には谷があった。その谷を越える赤い弧を描く橋が幾重にも幾重にも続いている。土産物屋の通りを端から端まで歩いた。
なにも手がかりは得られなかった。
結局我々の調査(と言ってもAliceは後を付いてくるだけで仕事をしているのは私だ)でも何も収穫は無かったのだ。私が聞いて回ってる間もAliceはぼやんとしたままで、何かの感情の類は感じ取れなかった。あたりは暗くなり始めていて、私は帰りたかった。なので、Aliceに帰るか、と問うとうなづいたので、もう帰ることにした。
Bettyにはどう報告するか。私はやるべきことはやったが手がかりは得られませんでした。残念でした。そう言うしかないだろうなと電子メールを打つ自分の姿を想像していた。
しばらく歩いてAliceの気配が無いような気がして後ろを振り返ると、Aliceは止まって谷の向こう側を目を細めて眺めていた。なにをしてんだよ、さっさと帰ろうやあ。そう思ってうんざりしているとAliceは意外なことを口にした。
「最後に、あそこ見たい」
馬鹿なりになにか思うところがあったのかと私は驚いて言葉に詰まった。指差した先、吊橋を挟んだ谷の向こう側に鳥居があって、その奥に長い階段が続いていた。
そう、いつかどこかで見た風景に似ていた。
Aliceとともに吊橋を渡って、鳥居をくぐった。階段を登り始めてすぐ、これはしんどいなとすぐに気づいた。その階段は長かった。あたりは暗くなり、先が見えないので永遠に続くのかと思った。階段をようやく登りきると、立派な神社が建っている。何か祭事でもあったのだろうか、通路に沿ってろうそくの火が灯されていた。しかし、人の気配は無かった。
Aliceは無言で賽銭を投げ入れ、手を合わせて頭を垂れた。ろうそくの光がAliceの頬で揺れていて、その表情は読み取れない。
熱心に手を合わせていたAliceは目をつぶって硬直していた。ずっと、そのままだった。私は石の階段に腰かけそれを待っていた。Aliceはゆっくりと顔を上げると暗い表情で私に近寄り、
「なぜ私はいつも一人だったのか」
と問うた。なぜいつも一人だったのか。Aliceの友達を見たことがない。Aliceが誰かと一緒に居るところを見たことがない。確かにAliceはずっと一人だった。なぜだろう。友達居ないのはなぜだったのだろう。Aliceが極度の方向音痴だったしいつもぼやんとしていて一緒に居てもつまらないからだろうな、と思ったが、言えなかった。
私は真面目な話が出来なかった。いつからか、友達とは素面で会えなくなった。それを恥ずかしいと思うようになった。いつもいつも酒が入った状態で現れ、消えていく友達。頭が痛い、気持ち悪い、喉が乾いたが水を飲んだら吐いてしまう、あらゆる悪酔いを我慢しながら、日々長い夜道を歩いて帰る私もAliceと同じで、いつからか一人になっていた。人のことは言えないな。そう思ったのだった。
だから、
「飲んで帰るか」
と答えた。なにも言えねぇんだ。
酒はうまくなかった。それは当然で、せっかく地方にきたのにその土地の旨いもの、旨い酒を調べるなどの行為をせず、すぐに見つけた全国展開のチェーン店に入ったからである。古びた町並みとは対象的に新しい看板を掲げていて、軽薄な感じだった。これが下調べしたあとに入った雰囲気のある飲み屋であったとしても、どちらにせよ、終始陰鬱な顔をした顔をした人間の前で陰鬱な気分の私が何を飲み食いしようと旨いものではない。
しばらくしてAliceは声を押し殺して泣き始めた。「お父さんやお母さんにもう一度会いたい」と情けないことを言う。情けないことを言わないでほしい、と、情けない気持ちでいる私が思った。
その時だった。
かすかな電子音を耳にした。初めは厨房かどこかから聞こえているのかと思ったが、それはどうも私のバッグから聞こえているようで、心当たりのない私は首をかしげながらバッグを手で探ると慣れない感触の物体がある。
幽霊探知機であった。よく見るとディスプレイの中央に緑の光点がかすかに揺れていて、それにはAliceと書いていた。その左右に二つの光点がある。
左にCheryl, 右にDavidと書かれていた。
私ははっと目の前を見たが、そこには焼き鳥に前髪を覆いかぶせて肩を震えている女がいるだけであった。探知機の表示はどう解釈すれば良いのだろうか。Aliceに伝えたほうが良いのだろうか。
つまり、幽霊探知機が本当に幽霊を探知する機械なのならば。いま、この瞬間は一人でないと?それはいつも一人だったと泣く女の慰めになるのだろうか?
そして、さらに。その上方に初めはごく薄く、しかし徐々にはっきりとした表示で光点と文字が探知機の画面に現れた。
Bettyと記されている。
「これが、最後のお願いになります」
そう言っていたBettyの顔が脳裏に浮かんだ。魔法使いみたいな、変な帽子を被っていた。
改めて周囲を見回しても、店員があくせくと串カツを運んでいるだけであった。
我々の旅は、それで終わりであった。
結局、私は幽霊探知機のことをAliceには伝えなかった。あいまいなまま店を後にし、帰りの新幹線に飛び乗り、Aliceを家まで送った。そのあとはもう電車が無かったのでタクシーを呼ぶか、歩いて帰るかを迷った後、歩くこととした。
喉が渇いていた。頭が痛かった。ふらふらと帰り道を歩いた。誰とも会わなかった。
そして次の日には二日酔いのために頭痛薬を飲んだ上で会社に向かった。仕事をするふりをしながら二日酔いが治るのをまった。そのあとはいつもの日常に足から頭の先まで浸かる。
徐々に幽霊探知機のことは忘れてしまったが、家の物置を探せばまだあるはずだ。もう、AliceともBettyとも連絡を取っていない。